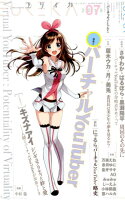タイトルにある通り、今日のネタはVTuberと創作です。
この二つを結びつけて何か書いている人ってあまりいないのではないかと思い、書いてみることにしたのですが、私の知らないところで「よくある話」になっていたりしたら嫌だなあ……そのときは広い心で百番煎じとして読んでいただけると嬉しいです。
VTuberの隆盛
私がVTuberを知ったのは、2017年の終わり頃の話ですね。
タイミングとしては、輝夜月さんがデビューしたのとほぼ同時期、いわゆる四天王という呼称が生まれて固まったあたりでしょうか。
特に早くもなければ遅くもない出会いだったように思います。
その後もそこそこ時間を割いて追いかけていたのですが、まあ業界の拡大……というか人数の増加には目を見張るものがありましたよね。
翌2018年になって最初の数ヵ月は、ある程度、界隈の全容を思い描くことができていました。
全員をチェックしていたわけではもちろんないのですが、だいたいこういうVTuberが有名で、こういうことをしている、という要所は掴めていたという意味です。
でもそれが同年後半に入ると、個人的にべつのことにリソースを割くことになった関係もあって、増加速度に認識がついていけなくなりました。
というか、その気持ちが湧いてこなくなった、というのが正確な表現になるでしょうか。
自分から新人のチェックに走ることは諦めて、然るべきメディアが「注目株」を取り上げたら、動画を一つ二つ観て、その名前を頭の片隅に入れておく、という受け身のスタイルに変わっていったのです。
(従ってこの記事は、VTuberにめちゃくちゃ詳しいから書いているわけではありません。そのあたりをご理解いただけると助かります)
そんな風に増加を続け、これを書いている今は8,000人を突破しているというVTuber。
正直なところ供給過多なところが若干あり、さほど多くないパイ(ファンとその可処分時間)を激しく奪い合っている感があるのですが、テクノロジーとしては非常に未来を感じる分野であり、その点では決していっときの流行で終わるものではないと私は思っています。
このまま永遠に増加していくとは思えませんし、だんだん個人系の頑張れる余地がなくなってきて「所詮は企業の道具」感に支配されてしまうこともあるかもしれませんが、全体として「滅ぶ」ことはないでしょう。
今後のさらなる展開に期待している所存です。
十人十色のキャラ設定
……という一応の説明パートを経たところで、ここからが本題です。
そんな具体にやたらめったら数が増えたVTuberですが、その結果として当然、その活動の在りようにも様々なかたちが見て取れるようになりました。
いろいろなことをやってみる系があれば、一つのジャンルに特化する系もある。歌あり絵あり諸種のコラボあり。豊富な特定知識を活かして本を出版する者も出てきました。
そういう状況の中、私は活動そのものよりも、もう少し根本的なところに注意が向くようになっていました。
VTuberの根幹「人間ではなくキャラである」ことを、各VTuberがどのような「設定」で処理しているか、その方法論の違いについてです。
あまりネタを割った話をするのは無粋な気もするのですが、言うまでもなく(ほとんどの)VTuberは生きた人間が動かし、喋ることによって成立しています。
その演者はしばしば「魂」と表現され、浄瑠璃の黒衣よろしく、「居て当たり前だし話題によっては触れもするが、平常時には存在しないことにしておく」ものとして扱われる。
それが業界、そしてファンの間での、暗黙の了解になっています。
しかしそれは言ってしまえば「ウソ」なわけです。
そのウソを維持し、キャラクターが独立的に動いている体裁を維持するためには、何かを言ったり言わなかったりする必要がある。
そこで用いられる「設定」の差異に、私は興味を持ったのです。
もう少し具体的に言うなら、設定の固め方に大きな強弱があるという事実と、それがもたらすコンテンツの傾向の違いに、自分の創作活動にも関わる興味深いものを感じた――という風になるでしょうか。
設定の功罪
どういうことかを説明するために、二人(一人と一組)のVTuberを例に挙げてみようと思います。
どちらも私が現在進行系で追っている数少ないVTuberで、以下どんな言い方をしていようと、基本的にファンであるということはご理解いただければと思います。
厳格な『キズナアイ』
まずはVTuber界の親分、キズナアイさん。
圧倒的なチャンネル登録者数を誇り、VTuberの顔として数々のメディアに取り上げられ、雑誌『ニューズウィーク日本版』では、特集記事「世界が尊敬する日本人100」にて、「注目すべき100人」の一人にも選ばれました。
押しも押されぬ、VTuberのシンボル的存在です。

しかし最近になって私は、その存在の仕方に、ある種の「窮屈さ」を感じるようになってきました。
これは他にVTuberがほとんどいなかった当初には抱かなかったものなのですが、だんだんと多種多様な同業者が増えていったことで浮き彫りになった要素です。
キズナアイさんは「インテリジェントなスーパーAI」という設定であり、年齢も活動開始からの年月を正確に反映したものにしている。AIだから人間のことを完全にはわかっておらず、人間の世界にも出てこられない。
そのあたりの「設定」を、きっちり作り込んでデビューした。
――であるがゆえに、主にリアルとの接続を必要とする企画において、面倒臭い(そして幾分白々しい)段取りを必要とする制約が生まれてしまったのです。
現実のどこかへ行くとなれば、誰かに行ってもらうか、バーチャルなマップで代用する必要がある。
何かを作るにしても――いやそれどころか荷物一つ開封するにしても、然るべきスタッフを用意し、その人にやってもらっているのだということを説明する必要がある。
ましてやYouTuberに定番の「食べる系」動画は完全にNG。
そういうのを「何も考えずにただ実行する」軽快な動画を作ることが、設定上とても難しくなってしまっているわけです。

私なりに言い換えるなら、設定に引っ張られて動画が重くなっている。
もちろんAIという設定から生まれるものだって無いわけではないでしょう。しかし私の観察する限りでは、特に最近では、そのことのメリットよりも、それによって動画に生まれる縛りの重さのほうが上回っているように感じられるのです。
設定を「ちゃんと作り込んだ」ことが、あらゆることにトライしてなんぼのYouTubeにおいては、生産性への悪影響として表れてしまっているわけですね。
余計なお世話ですが、チャンネル登録者数の割に動画の再生数が少ないのも、そのあたりが多かれ少なかれ関わっているのではないでしょうか。
フリーダムな『おめがシスターズ』
一方、その対極を為すような存在として活躍しているのが、双子VTuberのおめがシスターズさんです。
社会派VTuberを自称し、他のVTuberがやらないようなことにあえて切り込んでいくのが彼女らのスタイル。
その実験的な試みと、二人の仲の良さがよく表れた絶妙の掛け合いが、根強いファンを多数獲得しています。

おめがシスターズさんの設定は、とにかくゆるい。
きっちり固まっているのは、二人が双子の姉妹であることくらいではないでしょうか。
一応、演者の存在は隠していますが、キャラとしての二人はAIであるとも、他の何であるとも語られていません。
そして驚くべきことに、この二人はしばしばリアルの街へ繰り出し、通行人にインタビューを試みたり、カラオケで歌ったり、寿司屋で寿司を食べながら延々とだべったりするのです。

その際にはもちろん、「どういう理屈で外出が可能になっているのか」は適当に流されます。
「魂」の存在に言及することもなく、バーチャルとリアルの境目について何らかの説明を試みることもなく、ただ普通にかっぱ寿司を訪れてエビやサーモンを食らう。
当初は「『おめシスはいいぞ』と3回唱えると何故かリアルに行ける」という雑な段取りがあったのですが、最近ではもうそれすらもなく、当たり前のようにガンダムのフィギュアを買いに出かけて帰ってきたりします。
そして、それでもチャンネルはしっかり成立しているのです。
創作における設定
このようなスタイルの違いに触れるとき、私はそのことを、数年前から続けている小説の執筆と結びつけて考えてしまいます。
小説を書く際に何から作っていくかは、厳密に言えば人によりけりですし、各要素が細かく前後するのですが、多くの場合はまず、舞台やキャラクターを設定することから始まります。
その上でプロットを組み、本文を書き始めるというのが、王道的なやり方となるでしょう。
私もそのようにしているのですが……前々から悩んでいたことがありました。
それは、最初に作った設定が、後に物語を作ることを上手く促進させる場合と、逆に障壁となって停滞させる場合があり、そのどちらになるかが、設定作りの作業中にはまったく先読みすることができない、ということです。
理想的な設定がどんなものかと言えば、それを作ったお蔭でいろいろなことを思いつくことができ、それでいて思いついたことを何でも組み入れることができる、そんな魔法の箱のような設定です。
そういうのを自在に作ることができるなら、小説を書くことはかなり楽なものになりますし、また書いていて非常に楽しいものになるでしょう。
しかし現実的には、設定はアイディアを促す一方で、阻害もするのです。
その阻害がプロットの終盤に現れたときなどは、かなり悩むことになります。今からその阻害している部分だけ設定を変更して大丈夫か、他のどこかが破綻しないか、危険だからべつのアイディアが出てくるのを待つべきか――そんな葛藤に時間を取られることになる。
以前、キャラクターの履歴書を作ることが有効かどうか、について次のような記事を書きました。
このあたりがまさに、VTuber界隈の設定の硬軟に連なる問題です。
キャラクターをしっかり固めることで、語るべきことが重層的に浮かんできたり、事前に調べるべきことが見えてくることがある――理屈ではわかります。
しかし、私は上の記事で書いたように、キャラクターの履歴書を作るようになってから、逆に成績が落ちてしまった。
その一因として「細かく作ったところを守ろうとする意識に展開を阻害された」というのはあるのではないかと、素人なりに考えるわけです。
とはいえ、事前に設定を一切何も考えずに物語が作れるかというと、それもありません。
少なくとも私は(子供の頃にそれをやって何回か破綻した経験から言うのですが)物語を思いつくための何らかの指標を用意しなければ、それを完成まで持っていける自信はありません。
ここで大きな悩みに直面するわけです。
ある設定が、後に物語を作ることを促進させることになるのか、それとも阻害することになるのかを、あらかじめ判定する手段はないものだろうか、と。
その答は出ていないのですが、VTuberから一つ学べるのは、はじめから「ゆるくてもいい」物語を指向しておくというのが、一つのやり方なのかなということです。
やり方というか、逃げ道というか……つまり、面白い物語を考えることと同じかそれ以上に、「ブレを許容する物語を作ろうと心に決めておく」ことを重視するという意味ですね。
それによって作れる物語の方向性には限界が生まれると思うのですが、引き換えに「何でも入る」ものになりやすくなるのではないかと。
ちょうど今、そのようなことを考えながら、新たに新人賞に応募する小説の骨子をゆっくり考えているところです。
おわりに
VTuberの世界はまだいろいろな面で模索が続いており、キャラのアイデンティティもその一つとして未だ揺れているのでしょう。
今回の記事では構成の関係で触れませんでしたが、個人系VTuberだと、はじめから「魂」の存在をぶっちゃけている人もいます。また、声優の遥そらさんなどは、ご本人がそのままVTuberになっており、魂もへったくれもなかったりします。
さながら界隈そのものが、キャラクター造形に関する巨大な実験場です。
その空気が、少なくとも私には自分の創作のための、格好の教科書に映る。
これからも多様なVTuberさん達の動画を楽しみつつ、その存在の仕方について学べるところを学び、小説作りに活かしていきたいと思っています。
イラストで稼ぎたい人、イラストを依頼したい人はこちら